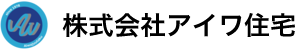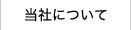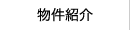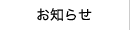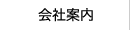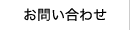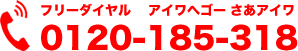小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」について、相続税の節税においてとても重要な制度ですので、分かりやすくご説明します。
■小規模宅地等の特例とは?
相続した土地が「自宅」や「事業に使っていた土地」である場合、一定の条件を満たせば、相続税の課税評価額を最大80%減額できる特例制度です。
これは、残された家族が住み続けたり、事業を継続したりするのに過大な税負担がかからないようにするための措置です。
■どれくらい減額されるの?
自宅用地(特定居住用宅地等) 80%減額 330㎡まで
事業用地(特定事業用宅地等) 80%減額 400㎡まで
貸付事業用地 50%減額 200㎡まで(※条件厳しめ)
■対象になる土地の種類
① 特定居住用宅地等(自宅)
- 被相続人が住んでいた土地
- 配偶者、同居していた子などが引き続き居住する場合に対象
② 特定事業用宅地等(事業)
- 被相続人が事業に使っていた土地
- 相続人が事業を引き継ぐ場合に対象
③ 貸付事業用宅地等(賃貸)
- 被相続人がアパートや駐車場などに貸していた土地
- 相続人が貸付事業を継続する場合(※要件厳しめ)
■具体例
たとえば、自宅の敷地評価額が6,000万円で、面積が330㎡以内の場合:
◆ 評価額 6,000万円 ×(1 - 0.8)= 1,200万円に圧縮!
→ この1,200万円に対して相続税がかかるため、大幅に節税できます。
■適用を受けるための主な要件(例)
自宅用地 相続人が配偶者 or 同居していた子などで、その後も住み続ける
事業用地 相続人が事業を継続する意思と実態がある
貸付用地 相続開始前3年以内に貸付を開始したものは原則対象外 など
※配偶者が取得する場合は、無条件で適用可能(例:自宅)
■手続き・申告について
この特例を使うには、相続税の申告書に特例の適用を申請する必要があります。
忘れると適用できないので要注意です!
■まとめ
メリット 土地の相続税評価額が最大80%減額
対 象 自宅、事業用、貸付用の土地(条件あり)
要 件 居住・事業継続、面積制限など
手続き 相続税申告で適用申請が必要
◆参考資料:国税庁「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」
相続税の基礎控除、配偶者特別控除
相続税の「基礎控除」と「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」について、ご説明します。
■相続税の基礎控除とは?
相続税には「基礎控除」という制度があり、相続財産がこの金額以下であれば、
相続税はかかりません。
■基礎控除の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
<例>
法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
→ 4,800万円までの遺産には相続税はかかりません。
■配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?
配偶者が相続する場合、特別に大きな控除(非課税枠)があります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。
■非課税限度額
配偶者が相続する財産については以下のどちらか大きい方まで非課税になります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分までの金額
つまり、配偶者が多くの財産を相続しても、一定の範囲なら相続税がかからないという制度です。
■例
配偶者と子ども1人が相続人 → 配偶者の法定相続分は 1/2
遺産が3億円の場合 → 配偶者が1億5,000万円を相続 → 非課税(法定相続分以下)
■注意点
- 配偶者控除を受けるには相続税の申告が必要です(ゼロでも申告しないと控除は適用されません)。
- 配偶者控除があるとはいえ、将来的な二次相続(たとえば配偶者が亡くなった後の相続)を考慮することも大切です。
国税庁
「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。
ご夫婦の相続
お子様がいないご夫婦の相続については、「配偶者がすべて相続するわけではない」という点がとても大切です。
多くの方が誤解しやすい部分でもあります。
■詳しくは、相続や不動産に強い私たちの公式サイトでもわかりやすく解説しています。
◆お子様がいない場合の相続の基本ルール(法定相続)
被相続人(亡くなった方)に子どもがいない場合、相続の対象になる親族の順番は以下のようになります:
- 配偶者は常に相続人(割合は状況により異なる)
- 子どもがいなければ、「親(直系尊属)」が相続人に
- 親がすでに亡くなっていれば、「兄弟姉妹」が相続人に
◆ 例で見る相続パターン
■ケース1:配偶者と両親が相続人の場合
- 配偶者:3分の2
- 両親:3分の1(両親で分け合う)
■ケース2:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(親がすでに他界)
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(複数人で分け合う)
◆注意ポイント
- 遺言書がなければ、民法に基づいて分けることになります。
- 配偶者が安心して自宅に住み続けるためにも、遺言書の作成が強く推奨されます。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者と面識がなくても法的な権利が発生するため、トラブルの原因になることもあります。
◆対策としておすすめなのは?
- 公正証書遺言の作成
配偶者にすべてを遺したい場合など、明確に意思を残せます。 - 任意後見制度や死後事務委任契約の活用
将来の介護や葬儀、財産整理もサポートできます。
お子様がいないご夫婦の相続は、遺言があるかどうかで結果が大きく変わる可能性があります。
ほかにも知りたいケースがあれば、遠慮なくご相談ください。
準確定申告
「準確定申告」について、ご説明します。
■準確定申告とは?
「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。
通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。
■なぜ必要なの?
亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。
■誰がやるの?
準確定申告は、相続人全員の連名で行います。
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。
■提出期限は?
被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。
例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限
■提出先は?
被相続人の住所地を管轄する税務署です。
■必要な書類:
- 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
- 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
- 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出
■申告が必要なケース例:
- 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
- 年金収入が400万円を超えていた
- 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
- 不動産や株の譲渡益があった
■注意点
- 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
- 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。
法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」について、ご説明します。
■法定相続情報証明制度とは?
「法定相続人が誰なのか」を法務局が公的に証明してくれる制度です。
相続の手続き(銀行・証券・不動産登記など)では、通常、戸籍を何通も提出する必要がありますよね?
それを簡略化するために、「法定相続情報一覧図」という1枚の証明書を使えるようにしたのがこの制度です。
■どんなときに使える?
相続が発生したあとの、以下のような手続きで利用されます:
- 銀行口座の解約
- 不動産の相続登記
- 株式・証券の名義変更
- 相続税申告 など
■どんな書類がもらえるの?
法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証付き)」です。
これを各機関に提出すれば、戸籍一式を毎回出さなくて済むようになります。
■手続きの流れ
- 戸籍一式を取得(被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍など)
- 「法定相続情報一覧図」を作成
- 登記所(法務局)に申出
- 法務局が確認・認証し、写しを交付
※手続きは無料!
※司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
■メリットまとめ
戸籍提出が1回で済む 毎回戸籍をコピーする手間がなくなる
無料で取得できる 認証手数料も不要
何枚でも写しを交付してもらえる 複数の金融機関に同時提出できる
手続きがスムーズに進む 書類チェックの時間が短縮
■注意点
- 法定相続情報一覧図の内容にミスがあると、再提出が必要
- 法定相続人が確定していないと使えない(相続放棄がまだの場合など)
■どこで手続きできる?
法務局(登記所)で、郵送や窓口で申出可能です。
全国どこの法務局でもOK(一部制限あり)
配偶者居住権
「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について、ご説明します。
■配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなるまで、または一定期間、無償でその住まいに住み続けられる権利です。
これは、2020年(令和2年)4月1日に施行された新しい制度で、高齢の配偶者の住まいを守るために導入されました。
■なぜ必要になったの?
これまでの制度では、住んでいた家も相続財産の一部として分割対象になるため、配偶者が「家を失う」リスクがありました。
特に、子どもとの遺産分割協議で不利な立場になることも…。
■そこで「配偶者の住む権利」を独立して保護するために、この制度が導入されました。
■どんな権利なの?
居住権の性質 所有権と別に設定される「使用権」
無償で住める 家賃などは不要
第三者に売却不可 譲渡・売却できない(保護目的の為)
法的保護あり 登記すれば第三者に対抗可能
■取得の方法は?
配偶者居住権は、以下のどちらかで取得できます。
- 遺産分割協議で定める
- 遺言で指定されている場合
■いずれの場合も、法務局で登記することで権利が保護されます。
■例で説明(簡単なケース)
夫が亡くなり、妻と子が相続人。
夫婦が住んでいた家の評価額は3,000万円。
【従来の方法】
妻が家を相続するなら、3,000万円分の他の財産が相続できなくなる(バランスが取りにくい)
【配偶者居住権を使った場合】
- 妻が「住む権利(配偶者居住権)」を取得 → 評価額はたとえば1,200万円
- 残りの1,800万円分の家の所有権は子どもに → 財産の分け方が柔軟になる
■メリット・デメリット
メリット
高齢の配偶者の住まいを確保できる
財産の分け方が柔軟になる
デメリット
不動産の評価や分割が複雑になる
家を売って現金化しにくくなる
■まとめ
- 2020年に施行された新しい制度
- 配偶者の「住まいを守る権利」として注目
- 相続人間のトラブル防止にも有効
- 遺言や遺産分割協議での事前の合意がポイント
自筆証書遺言書保管制度
■自筆証書遺言書保管制度とは
法務局では、自筆証書遺言書を安全に保管する制度を提供しています。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続時のトラブルを防ぐことができます。
■保管申請の手続き
1. 遺言書の作成
遺言書は、全文、日付、氏名を自筆し、押印する必要があります。パソコンで作成したものや録音は対象外です。
2. 保管申請書の作成
所定の保管申請書に必要事項を記入します。申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
3. 必要書類の準備
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
- 遺言書原本
- 保管申請書
4. 法務局への申請
遺言者本人が、遺言書保管所(法務局)に出向いて申請します。代理人による申請はできません。
■申請時の注意点
- 遺言書は、消すことのできない筆記具で記入してください。
- 遺言書の内容に不備があると、保管を拒否される場合があります。
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
相続登記申請義務化
2024年4月1日から施行された「相続登記の申請義務化」について、ご説明します。
■相続登記の申請義務化とは?
これまで、不動産の相続が発生しても「相続登記(名義変更)」をしなくても罰則がなかったため、長年放置されるケースが多く問題となっていました。
そこで、2024年4月1日から、相続による不動産の登記(名義変更)が義務化され、一定期間内に申請しないと**過料(罰金)**が科されることになりました。
■何が義務化されたの?
不動産を相続した人(相続人)は、取得を知った日から原則3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
■いつから?
◆ 2024年(令和6年)4月1日 から適用されています。
■罰則は?
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■対象になる人は?
- 相続で土地や建物を取得した人(法定相続・遺言・遺産分割問わず)
- 複数の相続人がいる場合は、各相続人ごとに申請義務があります
■過去の相続にも適用されるの?
はい、過去の相続も対象になります。
たとえば、昔の相続で名義変更がされていなかった場合でも、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。
■簡略的な手続きもあります
登記申請が難しい方のために、簡易的な「相続人申告登記」制度もあります。
これは、「自分が相続人である」と法務局に申告するだけで、申請義務を果たしたことになります(ただし名義変更ではないので注意)。
■まとめ:
義務化開始日 2024年4月1日
申請期限 相続を知ってから3年以内
罰 則 10万円以下の過料
対 象 相続で不動産を取得した全ての人
対象範囲 施行前の相続にも適用あり
◆相続登記は、司法書士に依頼することが多く、手続きが煩雑な場合は、当社にご相談下さい
遺産分割協議書
「遺産分割協議書」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合い、書面にまとめたものです。
■主なポイント
- 法的効力
遺産分割協議書は、相続登記や預金払い戻しなど、法的な手続きをする際に必要になります。 - 記載内容
- 被相続人の情報(氏名・死亡日)
- 相続人全員の氏名と住所
- 分割内容(どの財産を誰が相続するか)
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付
- 注意点
- 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると無効)
- 財産内容が不明確だと後にトラブルになることも