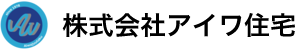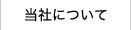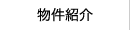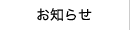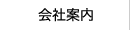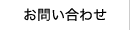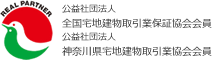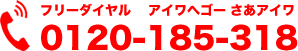容積率緩和の対象となる車庫の条件
中古不動産の購入における建築確認と既存不適格の注意点
中古住宅の売買では、建築確認申請書や検査済証の有無、また建物が当初の申請通りに建てられているかを確認することが重要です。
これらが整っていない場合や、建ぺい率・容積率がオーバーしている場合、金融機関によっては住宅ローンが利用できないことがあります。
建物が当時は合法でも、現在の建築基準法に適合しているかの調査が必要です。
これは、法令知識だけでなく、現場経験や実務判断力も求められます。
中古不動産仲介のポイント
中古不動産仲介では、新築や土地のみの取引と違い、建物そのものの知識が非常に重要です。
たとえば、容積率オーバーと思われる場合でも、以下のような緩和規定が存在します。
【1】容積率緩和の対象となる車庫の条件
以下のすべてを満たす場合、建物全体の延べ面積の1/5までの車庫部分は、容積率に算入されません:
- 建築物の1階部分に設けられていること
- 自動車の駐車のための用途に供されていること
- 住宅・共同住宅・店舗等に付属する車庫であること
△注意点:
- 車庫部分が店舗や事務所等として使われている場合は除外対象になりません。
- 実際には、所轄の建築主事や市区町村役所で確認を取ることが推奨されます。
【2】既存不適格建物について
既存不適格住宅とは:
「建築当時は法令に適合していたが、その後の法改正等により、現在の基準に適合しなくなった建物」のことです。
違法建築とは異なり、当初は合法だった点がポイントです。
✅ よくある既存不適格の例
- 用途地域の変更により容積率や建ぺい率を超えてしまった
- 道路拡幅などで、接道義務(2項道路等)を満たさなくなった
- 耐震基準改正により、構造上不適合(例:1981年以前の旧耐震基準)
✖違法建築との違い
既存不適格建築物:建築当時は適法 → 法改正により不適合になった
違法建築物:当初から建築基準法に違反(例:無許可増築、用途変更など)
△ 既存不適格住宅の注意点
- 利用:原則としてそのまま使用可能(ただし例外あり)
- 増改築:一定規模を超えると、現行法への適合が必要
- 建て替え:現行法に従う必要があり、同じ規模の再建不可の場合も
- 資産価値:売却や融資に不利な要因となるケースがある(金融機関の審査で減額対象に)
法的根拠
- 建築基準法 第3条第2項
→ 既存不適格建築物の継続使用を認める規定
→ ただし、「大規模の修繕・模様替え」「用途変更」「再建築」等では制限あり
省令準耐火
「省令準耐火(しょうれいじゅんたいか)」とは、日本の建築基準法に基づき、火災に対する一定の安全性能を満たした住宅の構造を指す用語です。正式には「準耐火構造に準ずる防火性能を有する住宅」という位置づけで、国土交通省の告示(省令)によって定められた基準を満たした建物を意味します。
省令準耐火構造の特徴
隣接する住宅からの延焼を防ぐため、屋根・外壁が不燃材料で作られている
- 内部の火災拡大を防ぐため、天井・壁が一定時間火を通さない素材で構成されている
- 各室間の防火区画が確保されており、火災時の延焼を遅らせる設計
- 木造であっても、石膏ボードなどの耐火被覆を使用して防火性能を高めている
■メリット
- 火災保険料が安くなることが多い(「省令準耐火構造」として扱われると保険会社の割引対象になる)
- 安全性が高く、万が一の火災にも強い
道路種別
【建築基準法 第42条の道路種別】
ア.第1項第1号道路(法定道路)
- 都市計画法等に基づいて道路として認定されている公道。
- 幅員4m以上(または6m以上)あることが多い。
- 最も基本的な公道で、問題なく建築可能。
イ.第1項第2号道路(旧道)
- 都市計画区域が指定された当時からすでに存在していた道路で、特定行政庁に認められたもの。
- 現在は法定道路に準ずる扱いを受ける。
- いわゆる「既存道路」とも呼ばれます。
ウ.第1項第3号道路(開発道路)
- 開発許可を得て造成された開発区域内の道路。
- 都市計画法の開発許可に基づいて整備され、建築基準法上の道路として認定されている。
エ.第1項第4号道路(事業計画道路)
- 都市計画により将来的に道路になる予定のもの。
- 公共事業の施行により道路として計画されているが、未完成の状態でも道路とみなされる場合あり。
オ.第1項第5号道路(位置指定道路)
- 個人や法人が私道を作る際に、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
- 一定の条件を満たすと建築基準法上の道路として認定される。
【第2項道路(いわゆる「2項道路」)】
カ.第2項道路(みなし道路)
- 建築基準法の施行以前から存在する幅員4m未満の道で、特定行政庁により道路とみなされたもの。
- 建築の際には道路中心線から2m(6m地区では3m)セットバックが必要。
- セットバック後の線が「敷地と道路の境界線」とされます。
【建築基準法第42条に該当しない道路】
キ.非該当道路(建築不可)
- 建築基準法第42条で定める道路に該当しない道。
- 原則として建築不可。ただし、接道義務を緩和する特例や、建築審査会の許可により例外が認められることも。
接道義務(建築基準法第43条)にも注意が必要です。
→ 幅4m以上の道路に2m以上接している必要あり(例外あり)
東京都建築安全条例(路地状敷地)
東京都建築安全条例 第3条(路地状敷地の形態)より
第三条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じ、次に定める幅員以上としなければならない。
一 20メートル以下のもの 2メートル
二 20メートルを超えるもの 3メートル
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合においては、その敷地の路地状部分の幅員は、前項に規定する幅員に1メートルを加えたもの以上としなければならない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物であって、その延べ面積の合計が200平方メートルを超えるもの
二 特殊建築物であって、その延べ面積の合計が100平方メートルを超えるもの
このように、路地状部分の長さや建物の用途・構造により幅員要件が異なるため、計画段階での確認が非常に重要です。
新耐震基準
「新耐震基準」とは、日本で1981年(昭和56年)6月に施行された建築基準法改正によって導入された耐震設計の基準です。この基準は、建物が震度6強〜7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを目指しています
■背景と特徴
- 旧耐震基準(1971年以前)
→ 「震度5程度の地震で損傷しないこと」が目安
→ 大地震時の倒壊リスクが高い - 新耐震基準(1981年以降)
→ 「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが基本方針
→ 構造体の設計に鉄筋や壁量の強化が盛り込まれた
■築年数での判断目安
1981年6月以前 旧耐震基準
1981年6月以降 新耐震基準(重要)
2000年以降 より厳格な改訂あり
■注意点
- 新耐震基準以前の建物でも耐震改修工事で補強が可能です。
- マンションや戸建ての購入時は「竣工日」や「検査済証」の確認が大切です
建蔽率容積率
建ぺい率(けんぺいりつ)と容積率(ようせきりつ)は、土地にどれだけ建物を建てられるかを定める重要な指標で、都市計画法および建築基準法によって規定されています
■ 建ぺい率(けんぺいりつ)
■ 定義
「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のこと
■ 計算式
建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50%
■容積率(ようせきりつ)
■定義
「敷地面積に対する延べ床面積(各階の合計床面積)の割合」のこと。
■ 計算式
容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、延べ床面積が150㎡なら、容積率は150%
■ 規制内容は用途地域ごとに異なる
第一種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100%または200%
商業地域 建ぺい率80% 容積率400%または500%
工業地域 建ぺい率60% 容積率200%または300%
※角地や防火地域の条件によって緩和される場合あり。
■土地を買う前、家を建てる前には、必ず都市計画図や役所の確認が必要です。
道路幅員による容積率制限とは
1. 道路幅員による容積率制限とは
建築基準法第52条第2項では、敷地が接している道路の幅が狭いと、建物の容積率(延べ床面積の制限)が自動的に下がるというルールがあります。
これは、日照・採光・通風などを確保するためです。
2. 基本ルール
容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、道路幅員による制限値の小さい方が適用されます。
道路幅員による制限値は、以下の式で計算します。
容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数容積率の限度 = 道路幅員(m) × 制限倍数容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数
この制限倍数は、用途地域によって異なります。
3. 制限倍数
- 住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)
→ 倍数は 4/10(=0.4)、つまり「道路幅員 × 0.4 × 100」でパーセント化
例:道路幅6mなら 6 × 0.4 × 100 = 240% - その他の用途地域(近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用)
→ 倍数は 6/10(=0.6)
例:道路幅6mなら 6 × 0.6 × 100 = 360%
4. 適用例
- 用途地域:第一種住居地域(倍数0.4)
- 指定容積率:300%
- 道路幅員:5m
計算:5 × 0.4 × 100 = 200%
→ この場合、300%ではなく**200%**が容積率の上限となります。
5. 注意点
- 接道している道路が複数ある場合は、幅員が最も広い道路側で計算します。
- 前面道路が4m未満の場合は、セットバック後の幅員で計算します。
- 指定容積率が道路幅員制限より低ければ、道路幅員制限は関係ありません。
斜線制限とは
1. 斜線制限とは
建物の高さを、一定の角度で制限する規定です。
周囲の日照・採光・通風を確保するために、建築基準法で定められています。
大きく分けて 3種類 あります。
2. 種類と内容
(1) 道路斜線制限
- すべての用途地域に適用
- 建物は、前面道路の反対側境界線から一定の角度で引かれた斜線内に収まる必要があります
- 基本は、道路中心線から1.25倍の高さまで(用途地域で係数や緩和あり)
- 例:幅員8mの道路 → 高さ制限は概ね10m(8m ÷ 2 × 1.25)
(2) 隣地斜線制限
- 住居系用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用など)に適用
- 隣地境界線から一定の角度で制限
- 開始高さは、第一種低層住居専用地域なら5m、中高層住居専用地域なら10mが一般的(自治体により異なる)
(3) 北側斜線制限
- 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用
- 北側隣地の日照確保のため、北側境界線から一定の角度で制限
- 開始高さは5mまたは10m、角度は1.25倍または1.5倍など自治体で設定
3. 緩和や例外
- 防火地域・準防火地域で耐火建築物にする場合は緩和あり
- 角地や道路幅員が広い場合、制限が緩やかになることがある
- 地区計画や高度地区の指定がある場合は、その規定が優先
4. 実務上のポイント
- 建築設計時は、建物の断面図に斜線を描いて確認するのが基本
- 道路・隣地・北側の制限が同時にかかることもあるため、組み合わせの検討が重要
私道使用承諾書
「私道掘削制限の緩和」とは、私道の下にライフライン(上下水道・ガス・電気など)を通すための工事を、一定の条件下で許可・緩和する措置のことです。
本来、私道は「私人の所有地」なので、勝手に掘削(=地面を掘ること)することはできません。
■ 私道掘削とは?
私道(私有地)に配管などを埋設したり、交換・修理するために地面を掘る行為のことです。
▲通常の私道掘削の制限
▲所有者の承諾が必要
掘削するには私道の所有者全員の書面による同意(私道承諾書)が原則必要
▲同意が得られないと工事できない
一人でも拒否する人がいれば、ライフラインの整備ができず、建築や居住に大きな支障が。
■掘削制限の緩和措置とは?
所有者の同意が得られない場合でも、公共の福祉やライフライン確保のために、一定条件で掘削を認める制度があります。
代表的な制度・方針
▲自治体による行政指導
「どうしても必要な工事」であると判断された場合、自治体が調整・指導を行うことがあります
▲都道府県・市区町村の条例・ガイドライン
一部自治体では、特定の要件を満たす場合に、私道掘削を認める規定を設けています
▲公共性の高い工事の場合
上下水道など、公益性の高いインフラ整備は、特例的に掘削が許可される場合があります
■ 緩和が認められるケースの一例
- 周辺の住民が最低限の生活インフラを必要としている
- 私道の使用が「不可避」で、他に代替手段がない
- 掘削部分の復旧が保証されている
- 掘削工事による私道の機能低下がないことが確認されている
■ 手続きの流れ(一般例)
- 掘削の目的・範囲を明示した計画書を作成
- 私道所有者への同意取得(できる範囲で)
- 自治体(市区町村)の道路管理課や建築指導課に相談
- 必要に応じて「特例承認」または「公共工事としての執行申請」へ進む
■ 注意点
- 緩和はあくまで例外措置で、自治体の判断に強く依存します。
- 私道の所有者が反対している場合は、裁判や調停に発展する可能性も。
- 掘削後の原状回復(舗装など)や近隣対応も大切です。
■ まとめ
「私道掘削制限の緩和」は、公私のバランスをとりながら、地域生活のインフラ整備を現実的に進めるための手段です。ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、事前に自治体への相談・調整が不可欠です。
必要であればあなたの自治体におけるガイドラインを調べたり、相談窓口をご案内することもできます。
参考資料:
- 東京都都市整備局 私道掘削に関する対応
- 各市区町村「私道掘削ガイドライン」等
市街化調整区域「既存宅地」
■ 市街化調整区域の既存宅地とは?
「市街化調整区域」とは、都市計画法によって定められた地域で、市街化を抑制し、計画的に緑地、森林、海岸などを保全すると共に農林水産における業務に支障を及ぼさないよう多様な建設を抑制するエリアのことです。
原則として、新たな建物の建築は厳しく制限されています。
しかし、建物の建築が許されるケースがあり、その代表が「既存宅地」です。
■ 既存宅地の定義とポイント
以下のような条件を満たす土地が「既存宅地」と認められる可能性があります。
- 昭和45年以前(都市計画法の施行以前)から宅地として使用されていた土地
- 過去に住宅が建っていたが、現在は空き地になっている土地
- 周囲に住宅が立ち並んでおり、地域的に一体性があると認められる場所