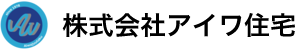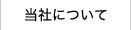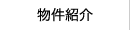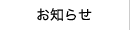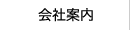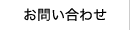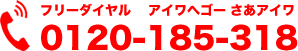有料個別相談のご案内
有料個別相談のご案内
当事務所では、一般のお客様を対象に
空き家・相続不動産・売却や活用に関する有料個別相談を行っております。
相模原市空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として、
行政相談・民間取引の両方に携わってきた経験をもとに、
一人ひとりの状況に合わせた現実的で具体的なアドバイスを行います。
「売るべきか残すべきか判断できない」
「相続したが、何から手を付ければよいかわからない」
「業者の話が正しいのか、第三者の意見がほしい」
このようなお悩みを、30分という限られた時間の中で
状況整理 → 選択肢の提示 → 今後の進め方まで分かりやすくご説明します。
有料相談の特徴
- 売却・媒介契約を前提としない、中立的な立場での相談
- 空き家の管理・活用・売却を含めた総合的な視点
- 図面・資料・登記内容を見ながらの具体的な助言
- 「今すぐやること」「急がなくてよいこと」を整理
無料相談では踏み込めない内容まで対応いたします。
料金・相談方法
相談料:30分 5,500円(税込)
完全予約制となります。
※30分単位での延長も可能です(事前にご相談ください)
※対面・オンラインいずれも対応可能です
ご利用にあたって
- 法律・税務に関する最終判断は、弁護士・税理士等の専門家への相談をおすすめする場合があります
- 無理な営業・契約の勧誘は行いません
- 相談内容の秘密は厳守いたします
こんな方におすすめです
- 空き家・相続不動産について、まず整理したい方
- 不動産会社の提案に不安があり、セカンドオピニオンがほしい方
- 具体的な方向性だけでも決めておきたい方
- ※上部の右端タブ「お問い合わせ」をクリックして下さい。
空き家の3,000万円特別控除
「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」
(被相続人の居住用財産の特例)
相続した空き家を一定の条件で売却すると、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
□制度の目的
- 相続後に放置される空き家の増加防止
- 老朽化による倒壊リスクの回避
- 早期流通の促進
根拠法:空家等対策の推進に関する特別措置法
所管:国税庁 国土交通省
主な適用要件(売主側)
① 相続した住宅であること
- 被相続人が一人で居住していた
- 昭和56年5月31日以前建築(旧耐震)
② 相続後の状態
- 事業・賃貸に使用していない
- 空き家である
③ 売却条件
- 売却価格1億円以下
- 相続開始から3年以内の年末までに売却
- 確定申告が必要
耐震要件(改正後のポイント)
現在は 3つの方法 のいずれかでOKです。
□ ① 売主が耐震改修して売却
→ 現行耐震基準を満たす状態で引渡し
□② 売主が解体して更地で売却
→ 建物を除却
□ ③ 購入者が取得後に耐震改修
→ 売却時は旧耐震のままでも可
→ 購入者が取得後に耐震改修し、基準適合証明を取得
この③が制度改正で追加された重要ポイントです。
購入者側のポイント
購入者が耐震改修を行う場合:
- 売買契約で「買主が耐震改修を実施する」ことを明確化
- 改修完了後に耐震基準適合証明書を取得
- 売主の確定申告に必要な書類を用意
改修費用は購入者負担
売主はその証明をもって3,000万円控除適用
実務上の注意
- 証明書取得期限に注意
- 他のマイホーム3,000万円特例との併用不可
- 共有相続は相続人ごとに適用可(条件あり)
土地や建物の譲渡所得
不動産などの資産を売却する際にとても重要です。「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」は、資産を保有していた期間(所有期間)によって分かれるもので、それによって税率も大きく変わります。
■ 長期譲渡所得 vs 短期譲渡所得
◆短期譲渡所得
5年以下 短期間の所有での売却。投機的とみなされ、税率が高い。
約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)
◆長期譲渡所得
5年超 長く保有した資産の売却。優遇税率が適用される。
約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
■ 所有期間のカウント方法
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」となります。
- カウントは「取得日から譲渡した年の1月1日まで」です。
■ 譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(※条件付き)
その後、長期 or 短期に応じた税率が適用されます。
■ 特別控除の例(長期譲渡所得で適用されやすい)
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 10年超保有の軽減税率の特例
- 買換え特例(一定条件で課税繰り延べ)
■ 補足
- 不動産の「登記日」ではなく実際の引渡日(契約成立日)が取得日とされます。
- 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得日・取得価格を引き継ぐルールがあります(取得費引継ぎ制度)。
年末調整、確定申告
年末調整とは?
「年末調整」は、会社員や公務員など給与所得者のために、会社が税金の過不足を調整する手続きです。
□特徴
- 対象:主に給与所得者(会社員など)
- 実施時期:12月(給与支払者が行う)
- 手続き:社員が「扶養控除申告書」などを提出し、会社が税金を計算
- 結果:源泉徴収で多く納めていれば還付、少なければ徴収
□控除対象例
- 配偶者控除、扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除 など
確定申告とは?
「確定申告」は、1年間の所得を自分で計算して、税務署に申告する制度です。
□特徴
- 対象:以下のような人
- 自営業、フリーランス
- 年収2,000万円超の給与所得者
- 給与以外に副収入がある人(副業など)
- 医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除初年度 など
- 実施時期:毎年2月16日〜3月15日
- 方法:e-Tax(電子申告)や紙での提出が可能
□控除や申告の目的
- 税金の還付(払いすぎた税金が戻る)
- 追加納税(足りなかった分を納める)
年末調整と確定申告の関係
- 会社員で年末調整だけで完結する人は、確定申告の必要なし
- 年末調整を受けた人でも、医療費控除やふるさと納税をした場合は、確定申告で還付が受けられることも
自宅を売った時の3,000万円特別控除
「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します
■ 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
■ 適用されるケース
- 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
■適用要件(主な条件)
- 売却した不動産が本人の居住用財産であること
- 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
- 過去に同じ特例を使っていないこと
- 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
- 家屋を取り壊した後でもOK
- 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
- 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
■ 控除の計算方法(簡単な例)
例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円
【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円
【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません)
■ 他の特例との併用について
- 「軽減税率の特例」とは併用できません
- 「買換え特例」などとは併用不可
- どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
■ 手続きの方法
- 確定申告が必要です!
- 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
- 「譲渡所得の内訳書」などを添付
■ 注意点
- 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
- 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます
不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
告知義務
「超高齢化社会における不動産取引における孤独死の告知義務」について、国土交通省のガイドラインを基に説明します
■告知義務の基本的な考え方
2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、孤独死を含む人の死に関する告知義務の基準が明確化されました
■告知義務が原則不要なケース
- 自然死(老衰や病死)や、日常生活の中での不慮の事故死(転倒事故、誤嚥など)で、かつ特殊清掃等が行われていない場合は、原則として告知義務はありません。
自宅における死因のうち、老衰や病死による死亡が9割以上を占める一般的なものであるため、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えます
▲ 告知義務が必要となるケース
- 自殺、他殺、火災による死亡など、事件性のある死が発生した場合
- 自然死や不慮の事故死であっても、遺体の発見が遅れ、特殊清掃や大規模なリフォーム等が行われた場合。
- 死因が明らかでない場合(自然死か自殺・他殺か判断できない場合)
これらの場合、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告知義務が生じます
■告知義務の期間
- 賃貸借取引において、上記の告知義務が必要な事案が発生してから概ね3年が経過した後は、原則として告知義務は不要とされています。
- ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案については、3年経過後も告知が必要となる場合があります。
告知義務の有無や期間については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります。全宅連
■ 告知の方法と内容
- 告知を行う際には、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた場合はその旨を伝える必要があります。
- ただし、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。
宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して告知書等への適切な記載を求め、これを買主・借主に交付することが、トラブルの未然防止と迅速な解決のためにも有効です
■まとめ
▲自然死(老衰・病死)
告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合
▲日常生活の中での不慮の事故死
告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合
▲自殺・他殺・火災による死亡
告知義務必要 事件性があるため
▲自然死や不慮の事故死でも特殊清掃等が行われた場合
告知義務必要 遺体の発見が遅れた場合等
▲死因が明らかでない場合
告知義務必要 自然死か自殺・他殺か判断できない場合
▲告知義務が必要な事案発生から3年経過後(賃貸借取引)
告知義務原則不要 事件性、周知性、社会的影響等が特に高い場合を除く
■告知義務の有無や内容については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります
参考:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」
令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課