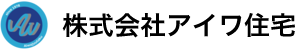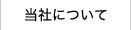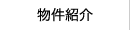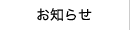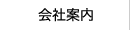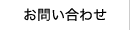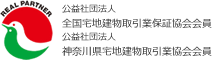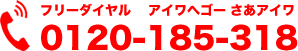収支シミュレーションの見直し
収支シミュレーションの見直し
築年数が経っている物件では、単純な「表面利回り」だけではリスクを見逃してしまうことがあります。
以下の点に注意して、より現実的なキャッシュフロー予測を立てる必要があります。
1. 修繕費の見込み
- 築古物件では、給排水管の交換や外壁塗装、屋根補修など大きな修繕が近づいていることが多いです。
- 数百万円単位の費用がかかる場合もあるため、事前に専門家に見積もりを依頼しておくと安心です。
2. 家賃下落の可能性
- 築年数が古くなるほど、家賃の下落リスクが高まります。
- 物件周辺の家賃相場と比較して、今後どの程度下がる可能性があるかを把握しましょう。
3. 空室率の上昇
- 築古物件は入居希望者が少なくなりがちで、空室期間が長期化することもあります。
- 地域の空室率や入居ニーズ(学生、単身者、高齢者など)も要チェックです。
4. 固定費の増加
- 古い物件は保険料が高くなる傾向があります。
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)も築年数とともに上がる場合があります。
5. 節税効果の過信に注意
- 築古物件は減価償却による節税メリットが強調されがちですが、実際の現金支出が多ければ赤字になる可能性も。
- 節税だけで判断せず、現金の出入り=実質収支に注目しましょう。
■現実的な収支シミュレーション例
年間家賃収入 600万円と仮定
空室ロス(10%) -60
管理費・共益費 -50
修繕積立・予備費 -80
固定資産税 -30
火災保険 -10
融資返済 -250
年間収支合計 +120
※ これは一例であり、実際はもっと詳細な項目と精度の高い見積もりが必要です。
築古物件を買うなら、「利回りが高い=儲かる」ではないことをしっかり意識し、「将来的な支出やリスクを織り込んだシミュレーション」が成功の鍵です。
連帯保証人
賃貸契約に関する保証制度、特に連帯保証人制度の見直しについて、説明します。
1. 連帯保証人とは?
連帯保証人は、借主が賃料を支払わなかったり契約違反をした場合、借主と同じ責任を負う人です。債権者(この場合オーナーや管理会社)は、借主に請求せず直接連帯保証人に請求できるほど、責任が重い立場にあります。
2. 制度の見直し(民法改正)について
2020年4月1日に施行された改正民法により、個人が連帯保証人になる場合、次のような制限が加わりました。
■ 極度額の設定が義務化
- 個人が連帯保証人になる場合、「極度額」(保証の限度額)を契約書に明記しなければ、その保証契約は無効になります。
- これにより、連帯保証人は無制限な責任を負わされるリスクが軽減されました。
3. 極度額とは?
- 例えば、「極度額300万円」と明記されていれば、借主がいくら滞納しても、連帯保証人に請求できるのは最大300万円までです。
- 家賃が月10万円であれば、30か月分(=2年半)までの滞納分が限度、というイメージです。
4. 滞納が何か月で連帯保証人に通知されるか?
これは契約内容や管理会社の運用によります。一般的には:
- 1~2か月滞納時点で借主・連帯保証人に連絡が行くケースが多いです。
- 連帯保証人への通知義務は法律で明記されているわけではありませんが、適切なタイミングで通知することが求められています。
5. 2か月以上の支払義務違反と契約解除
- 契約書に「2か月以上賃料を滞納した場合、契約解除できる」とあれば、貸主はその時点で契約解除できます。
- しかし、貸主が何か月も滞納状態を放置した場合でも、連帯保証人に極度額までの請求はできます。
6. 空き家状態が続いていた場合は?
- 借主が退去せず、長期間家賃を滞納し続け、かつオーナーが対応しなかった場合でも、連帯保証人には極度額までの責任が生じる可能性があります。
- ただし、貸主の「損害拡大回避義務」に反する場合は、保証人の責任が軽減される可能性もあります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連帯保証人の責任 | 借主と同等。ただし極度額の範囲内。 |
| 極度額 | 契約時に必ず明記。上限のこと。 |
| 通知時期 | 多くは1~2か月の滞納で通知。 |
| 空き家が続いた場合 | 責任はあるが、貸主の対応状況によって減免可能性あり。 |
収益還元法
■収益還元法とは?
収益還元法(しゅうえきかんげんほう)は、不動産や企業の価値を評価する手法の一つで、
将来的に得られると予測される収益を現在の価値に割り引いて評価する方法です。
■具体的にはどういうこと?
この方法では、次のようなステップで評価を行います:
① 収益の見積もり
その資産(例:賃貸マンションやオフィスビル)から将来得られる年間の純収益(NOI)を計算します。
- 回り(キャップレート)の設定
投資家が期待する利回りを設定します。たとえば5%など。
③ 価値の算出
次の式を使って評価額を計算します:
■収益還元法の種類
- 直接還元法:単年の純収益を還元利回りで割って価値を算出。
- DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法):将来の複数年分のキャッシュフローを現在価値に割引いて評価。
■どんなときに使うの?
- 不動産鑑定評価(賃貸不動産など)
- M&A(企業買収時の企業価値評価)
- 投資判断(株式やREITなど)
■収益還元法の事例:賃貸マンションの評価
所在地:東京都内
- 1Kタイプの部屋が10戸あるマンション
- 月額賃料:1戸あたり8万円
- 空室率:5%
-
年間運営費:100万円
① 年間総収入(GPI)
8万円×10戸×12ヶ月=960万円
② 空室損失・滞納損失(5%)
960万円× 5% = 48万円
③ 実効総収入(EGI)
960万円−48万円=912万円
④ 純収益(NOI)
912万円−100万円(運営費)=812万円
⑤ 還元利回り(例:5%)
⑥ 収益還元法による評価額
812万円÷0.05=1億6240万円
■結果
このマンションの評価額は 約1億6,240万円 になります。
修繕積立金・予備費の目安(年間)
修繕積立金・予備費の目安(年間)
一般的な目安としては、以下の通りです:
修繕積立金 家賃収入の5~10% 外壁・屋根・設備などの将来修繕に備える
予備費(緊急修理など) 家賃収入の3~5% 給油器故障・漏水など突発的な支出に備える
※ 例えば年間家賃収入が600万円のケース:
- 修繕積立金:600万円 × 10% = 60万円
- 予備費:600万円 × 5% = 30万円
- 合計:年間90万円(15%)を保守的に確保するのが理想的
注意点
- 築年数が古いほど割合は高めに見積もるべきです(15%〜20%を想定してもよい)。
- 区分マンションの場合は管理組合で積み立てている修繕積立金が別途あるため、確認が必要。
- 一棟物件ではオーナー自身が責任を持って備える必要があるため、現実的に数年ごとの修繕計画を立てておくと安心です。
結論として、家賃収入の10〜15%を目安に修繕・予備費を積み立てるのが健全な経営と言えます。
これを怠ると、突発的な支出でキャッシュフローが急激に悪化するリスクがあります。
民法と借地借家法の退去通知
民法第617条(令和2年改正後の条文)
この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。
特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。
■第617条(賃貸借の解約申入れ)
第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる。
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、
- 建物の賃貸借では3か月
- 土地の賃貸借では1年
を経過することによって、契約は終了する。
■要点まとめ
①期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)
②当事者はいつでも通知できる
③建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後
④この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます
▲借地借家法との関係
①借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません。
- ②正当事由が必要
- ③通知は原則6か月前
- ④借主の保護が優先される
■「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です
借地借家法退去通知6か月
貸主(家主)が賃貸借契約を解除する、つまり借主に退去を求める場合には、民法や借地借家法の規定に従う必要があります。
◆貸主による契約解除の基本ルール
- 正当事由が必要(借地借家法 第28条)
- 貸主が一方的に契約を解除したり、更新を拒否するためには、「正当な理由(正当事由)」が必要です。
- 例:建物の老朽化、貸主自身や親族が住む必要がある、長期間の家賃滞納など。
- 単に「貸したくなくなった」「売却したい」などの理由だけでは不十分とされることが多いです。
- 通知期間の目安
- 通常、6ヶ月前までに通知する必要があります(特に定期借家でない普通借家契約の場合)。
- 契約内容や地域の慣習によって異なる場合もありますが、「3ヶ月前通知」は基本的には短すぎると判断される可能性が高いです。
- 裁判での判断
- 借主が納得せず退去を拒んだ場合、裁判での判断になります。
- 裁判所は「正当事由の有無」「通知時期」「借主側の不利益の程度」などを総合的に考慮します。
■まとめ
- 「3ヶ月前通知(民法)で退去させる」は基本的に認められにくい。
- 正当事由が必要で、一般的には6ヶ月以上前に通知が望ましい。
- 借主の権利は強く保護されているので、専門家(弁護士や宅建士)に相談するのが安全です。
民法退去通知3か月
■民法の規定(民法第617条など)
- 民法では、「期間の定めのない賃貸借」の場合、解約申入れの通知から3か月経過で終了とされています。
- 貸主が「契約を終了したい」と申し入れた場合、原則として3ヶ月前の予告で契約を終了させられるという規定はあります。
◆これが「民法では3か月」と言われる理由です。
▲ただし注意!借地借家法が優先される
民法のルールは基本ですが、借地借家法という特別法があり、これが賃貸住宅の契約には優先されます。
借地借家法では:
- 貸主が解約や更新拒絶をするには「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)。
- 通知は少なくとも6ヶ月前が通例(特に更新拒絶時)です。
- つまり、「3ヶ月前に通知したからOK」とはならないのです。
■結論
- 民法上は3ヶ月で解約可という規定がありますが、
- 借家契約では借地借家法が優先され、「正当事由」+通常は6ヶ月前通知」が必要です。
- 実務上、民法の「3か月規定」だけで借主を退去させるのは極めて困難です。
家賃保証制度
日本の賃貸制度における「保証会社」について、以下のように詳しく、わかりやすく解説いたします。
◆ 日本の賃貸住宅における保証制度とは?
以前の日本では、賃貸契約時に「連帯保証人(家族や知人)」の署名・捺印が必須でした。
特に家賃滞納があった場合、この連帯保証人が責任を負う仕組みでした。
しかし現在では、「保証会社(家賃保証会社)」を利用するケースが一般的となっています。
◆ 保証会社の仕組み
- 借り主が保証会社に申し込みます(賃貸管理会社や不動産会社経由で行います)
- 保証会社が借り主の収入や職業、在留資格などを審査します
- 審査に通過すれば契約可能、連帯保証人が不要になる場合が多いです
- 万一の家賃滞納が発生しても、保証会社が家主に家賃を立て替えます
◆ 保証会社は後に、借り主に対して立替分の請求を行います。
◆ 外国人の方も借りられる?
はい、保証会社の審査に通れば、外国人の方でも日本で物件を借りることが可能です。
外国籍の方に対して審査で重視されるポイント:
- 在留資格の種類と期間
- 職業や収入の安定性
- 日本語での意思疎通能力
- 過去の滞納歴の有無
◆保証会社によっては、英語や中国語、ベトナム語など多言語対応をしているところもあります。
◆管理会社・オーナーの安心材料にも
賃貸管理会社は、借り主の家賃滞納リスクを減らすために保証会社を活用しています。
保証会社の承認があることで、貸し手側も安心して契約できます。
このように、「保証会社制度」は、借り主・貸し主の双方にとってメリットのある仕組みです。
他に気になる点があれば、何でもお気軽にご相談ください。