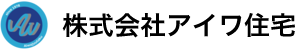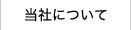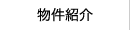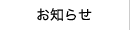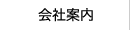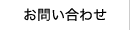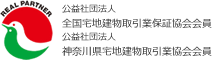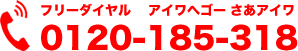省令準耐火
「省令準耐火(しょうれいじゅんたいか)」とは、日本の建築基準法に基づき、火災に対する一定の安全性能を満たした住宅の構造を指す用語です。正式には「準耐火構造に準ずる防火性能を有する住宅」という位置づけで、国土交通省の告示(省令)によって定められた基準を満たした建物を意味します。
省令準耐火構造の特徴
隣接する住宅からの延焼を防ぐため、屋根・外壁が不燃材料で作られている
- 内部の火災拡大を防ぐため、天井・壁が一定時間火を通さない素材で構成されている
- 各室間の防火区画が確保されており、火災時の延焼を遅らせる設計
- 木造であっても、石膏ボードなどの耐火被覆を使用して防火性能を高めている
■メリット
- 火災保険料が安くなることが多い(「省令準耐火構造」として扱われると保険会社の割引対象になる)
- 安全性が高く、万が一の火災にも強い
道路種別
【建築基準法 第42条の道路種別】
ア.第1項第1号道路(法定道路)
- 都市計画法等に基づいて道路として認定されている公道。
- 幅員4m以上(または6m以上)あることが多い。
- 最も基本的な公道で、問題なく建築可能。
イ.第1項第2号道路(旧道)
- 都市計画区域が指定された当時からすでに存在していた道路で、特定行政庁に認められたもの。
- 現在は法定道路に準ずる扱いを受ける。
- いわゆる「既存道路」とも呼ばれます。
ウ.第1項第3号道路(開発道路)
- 開発許可を得て造成された開発区域内の道路。
- 都市計画法の開発許可に基づいて整備され、建築基準法上の道路として認定されている。
エ.第1項第4号道路(事業計画道路)
- 都市計画により将来的に道路になる予定のもの。
- 公共事業の施行により道路として計画されているが、未完成の状態でも道路とみなされる場合あり。
オ.第1項第5号道路(位置指定道路)
- 個人や法人が私道を作る際に、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
- 一定の条件を満たすと建築基準法上の道路として認定される。
【第2項道路(いわゆる「2項道路」)】
カ.第2項道路(みなし道路)
- 建築基準法の施行以前から存在する幅員4m未満の道で、特定行政庁により道路とみなされたもの。
- 建築の際には道路中心線から2m(6m地区では3m)セットバックが必要。
- セットバック後の線が「敷地と道路の境界線」とされます。
【建築基準法第42条に該当しない道路】
キ.非該当道路(建築不可)
- 建築基準法第42条で定める道路に該当しない道。
- 原則として建築不可。ただし、接道義務を緩和する特例や、建築審査会の許可により例外が認められることも。
接道義務(建築基準法第43条)にも注意が必要です。
→ 幅4m以上の道路に2m以上接している必要あり(例外あり)
東京都建築安全条例(路地状敷地)
東京都建築安全条例 第3条(路地状敷地の形態)より
第三条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じ、次に定める幅員以上としなければならない。
一 20メートル以下のもの 2メートル
二 20メートルを超えるもの 3メートル
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合においては、その敷地の路地状部分の幅員は、前項に規定する幅員に1メートルを加えたもの以上としなければならない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物であって、その延べ面積の合計が200平方メートルを超えるもの
二 特殊建築物であって、その延べ面積の合計が100平方メートルを超えるもの
このように、路地状部分の長さや建物の用途・構造により幅員要件が異なるため、計画段階での確認が非常に重要です。
擁壁所有者
■擁壁の所有者を判断するポイント
① 擁壁がどちらの土地に属しているか
擁壁の設置位置が境界線のどちら側にあるかによって、所有者が判断されることがあります。
- 擁壁が片側の土地に完全にある → その土地の所有者が擁壁の所有者
- 擁壁が境界線をまたいで設置されている → 両方の所有者で共有している可能性あり
-
◇大きな高低差のある分譲地等の多くは、区画を考えてから工事をします。
境界杭を打ち付けて工事をしても実際は無理なので、造成工事が終わってから境界の杭を打ちます。
作成した図面通りに登記申請すると擁壁の間が境界になる事があります。
擁壁全てを上敷地所有者のもの、下敷地所有者のものではなく、その杭から境界になります。(擁壁は共有)
② 擁壁の目的と造成の経緯
擁壁が「どちらの土地を支えるために作られたのか」も重要です。
- 高い土地の所有者が土を崩さないように造成した → 高い方の土地の所有者が設置したとされ、所有者になるケースが多い
- 低い土地の所有者が土砂の侵入を防ぐために設置した → 低い方の所有者が設置した可能性あり
⛏ 実際には、開発業者や造成時の資料(開発許可図面、境界確認書、登記簿など)を確認する必要があります。
③ 登記簿や土地境界図で確認
- 擁壁そのものが建物ではないため、登記されていないことが多いですが、土地の登記簿や実測図などで境界線や擁壁の位置が確認できる場合もあります。
- 不動産調査士や土地家屋調査士に相談して、「境界標(杭)」の位置を確認するのが確実です。
よくあるトラブルと注意点
- 擁壁の修繕や崩落時の責任については、所有者の責任になる可能性があります。
- 共同利用している場合でも、誰が修繕費を出すかでトラブルになることがあります。
- 不動産の売買時にも、擁壁の所有・管理責任の確認は重要です。
■まとめ:擁壁の所有者は?
擁壁の位置 境界線のどちら側かを確認
造成の経緯 どちらの土地のために作られたか
登記・図面 登記簿や実測図、境界標を確認
不明な場合は、不動産専門家に相談するのがベストです
ご夫婦の相続
お子様がいないご夫婦の相続については、「配偶者がすべて相続するわけではない」という点がとても大切です。
多くの方が誤解しやすい部分でもあります。
■詳しくは、相続や不動産に強い私たちの公式サイトでもわかりやすく解説しています。
◆お子様がいない場合の相続の基本ルール(法定相続)
被相続人(亡くなった方)に子どもがいない場合、相続の対象になる親族の順番は以下のようになります:
- 配偶者は常に相続人(割合は状況により異なる)
- 子どもがいなければ、「親(直系尊属)」が相続人に
- 親がすでに亡くなっていれば、「兄弟姉妹」が相続人に
◆ 例で見る相続パターン
■ケース1:配偶者と両親が相続人の場合
- 配偶者:3分の2
- 両親:3分の1(両親で分け合う)
■ケース2:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(親がすでに他界)
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(複数人で分け合う)
◆注意ポイント
- 遺言書がなければ、民法に基づいて分けることになります。
- 配偶者が安心して自宅に住み続けるためにも、遺言書の作成が強く推奨されます。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者と面識がなくても法的な権利が発生するため、トラブルの原因になることもあります。
◆対策としておすすめなのは?
- 公正証書遺言の作成
配偶者にすべてを遺したい場合など、明確に意思を残せます。 - 任意後見制度や死後事務委任契約の活用
将来の介護や葬儀、財産整理もサポートできます。
お子様がいないご夫婦の相続は、遺言があるかどうかで結果が大きく変わる可能性があります。
ほかにも知りたいケースがあれば、遠慮なくご相談ください。
さまざまな種類の保険
保険にはさまざまな種類があり、それぞれが特定のリスクに備えるための仕組みです。日本で一般的な保険の種類を簡単に説明します:
✅生命保険(せいめいほけん)
万が一の死亡や高度障害時に保険金が支払われ、遺族の生活を支える保険です。
- 定期保険:保険期間が決まっている(安価)
- 終身保険:一生涯保障される(貯蓄性あり)
- 収入保障保険:毎月一定額が支払われるタイプ
✅医療保険・がん保険
病気やけがによる入院・手術に対する給付金が支払われます。
- 医療保険:一般的な入院や手術に対応
- がん保険:がんと診断されたときの治療費用をカバー
✅ 自動車保険(じどうしゃほけん)
自動車事故に備える保険で、加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。
- 対人・対物賠償
- 車両保険
- 人身傷害補償など
✅ 火災保険・地震保険
自宅が火事や自然災害で被害を受けた場合に補償されます。
- 火災保険:火災・風災・水漏れなど
- 地震保険:地震・津波による損害(火災保険とセットで契約)
✅ 介護保険(かいごほけん)
公的保険制度の一部で、40歳以上が加入対象。要介護になった際に介護サービスを受けるための支援です。
ご自身のライフステージや目的に応じて、適切な保険を選ぶことが大切です。
新耐震基準
「新耐震基準」とは、日本で1981年(昭和56年)6月に施行された建築基準法改正によって導入された耐震設計の基準です。この基準は、建物が震度6強〜7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを目指しています
■背景と特徴
- 旧耐震基準(1971年以前)
→ 「震度5程度の地震で損傷しないこと」が目安
→ 大地震時の倒壊リスクが高い - 新耐震基準(1981年以降)
→ 「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが基本方針
→ 構造体の設計に鉄筋や壁量の強化が盛り込まれた
■築年数での判断目安
1981年6月以前 旧耐震基準
1981年6月以降 新耐震基準(重要)
2000年以降 より厳格な改訂あり
■注意点
- 新耐震基準以前の建物でも耐震改修工事で補強が可能です。
- マンションや戸建ての購入時は「竣工日」や「検査済証」の確認が大切です
準確定申告
「準確定申告」について、ご説明します。
■準確定申告とは?
「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。
通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。
■なぜ必要なの?
亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。
■誰がやるの?
準確定申告は、相続人全員の連名で行います。
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。
■提出期限は?
被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。
例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限
■提出先は?
被相続人の住所地を管轄する税務署です。
■必要な書類:
- 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
- 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
- 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出
■申告が必要なケース例:
- 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
- 年金収入が400万円を超えていた
- 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
- 不動産や株の譲渡益があった
■注意点
- 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
- 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。
終身医療保険
終身医療保険は、人生を通じて医療リスクに備えることができる保険で、多くの方に選ばれている保険商品です。以下では、終身医療保険の主な利点をわかりやすくご紹介します。
■ 終身医療保険の利点(メリット)
① 一生涯保障される
- 契約期間に終わりがなく、死亡するまで保障が続く。
- 高齢になってからの入院や手術にも対応できる。
② 保険料が一定(多くは「終身払」または「短期払い」)
- 若いうちに加入すると、その時点の保険料が一生変わらないケースが多い。
- 老後の医療費不安に備えやすい。
③ 解約返戻金があるタイプもある(※商品による)
- 掛け捨て型ではないタイプなら、途中で解約した際に戻るお金(返戻金)があることも。
- 将来的な資金としての活用も可能。
④ 高額療養費制度を補完できる
- 公的医療保険だけではカバーできない差額ベッド代・先進医療費・通院費用などにも備えられる。
⑤ 特約で保障をカスタマイズ可能
- 例:がん特約、先進医療特約、通院保障などをニーズに合わせて追加できる。
- 自分や家族の病歴に応じて柔軟に設計可能。
■ こんな人におすすめ
▲若いうちに加入したい人 保険料が安く、将来の医療リスクに早めに備えられる
▲老後の医療不安がある人 高齢期の入院・手術費用への備えができる
▲長期の安心を求める人 保険の更新手続きが不要で、安心感が持てる
⚠️ 注意点(デメリットもチェック)
- 保険料は定期型より高め(長期保障のため)
- 若いうちに医療費がかからなければ、元が取れないと感じることも
- 加入時の健康状態により、加入できない・制限がある場合も
土砂災害警戒区域と盛土法の調査
- 市役所の調査で足りない、県土木事務所調査
- なぜ県の所轄になるのか
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づいて都道府県知事が指定します。
- 盛土規制法(盛土規制区域)も同様に、都道府県が管轄しています。
- そのため、最新かつ正式な区域情報や図面は県土木事務所(または県の都市計画課など)にしかありません。
- 市役所でできること
市役所は直接の所轄ではないため、「公式な証明」や「最新図面の交付」は基本的にできませんが、
次のようなことはできる場合があります。
- 都市計画課や建築指導課で、参考資料として区域図を閲覧できることがある
→ 市が県からデータを受け取っている場合 - ハザードマップ(防災課・危機管理課)での確認
→ 土砂災害・浸水・津波などの危険区域を市民向けに案内 - 担当課から県土木事務所への電話確認の依頼
→ 市役所の窓口職員が、直接県に問い合わせてくれるケースもあります
- 時間の問題への対応策
- 事前に県土木事務所へ電話予約・メール依頼
→ 資料を先にPDFで送ってもらえる場合があります - 市役所調査の前に、午前中に県へ確認
→ 先に県の資料を押さえておけば、市役所での調査と照合可能 - 不動産調査代行業者を活用
→ 平日16時までに行けない場合の代替策として有効
- まとめ
- 市役所では公式な証明は出せないが、参考情報やハザードマップの提示は可能な場合がある。
- 正式な調査結果や証明書が必要なら、必ず県土木事務所で確認する必要がある。
- 時間が合わない場合は、事前予約・資料送付依頼・代理人調査で対応するのが現実的。