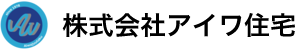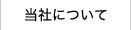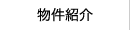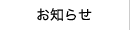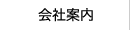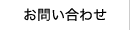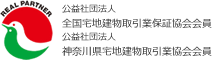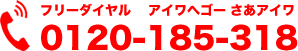住宅ローン
住宅ローン
■ 1. 資金計画の確認
- 自己資金(頭金):一般的には物件価格の10〜20%程度が望ましいですが、最近は「フルローン」や「諸費用ローン」も可能なケースがあります。
- 年収と返済比率の確認:
- 銀行は「返済負担率(年間返済額 ÷ 年収)」で審査します。
- 目安:年収の30〜40%以内に収まるケースが多いです。
- ■ 2. 金融機関の比較と事前審査
- 主な金融機関:
- メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな)
- ネット銀行(住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、pay pay銀行など)
- 地方銀行・信用金庫
- 比較項目:
- 金利(変動/固定)
- 保証料・団信(がん特約付きなど)
- 繰上返済手数料
- 事前審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 源泉徴収票または確定申告書(直近1~2年分)
- 物件資料(売買契約前でも可能)
■ 3. 購入物件の決定と売買契約
- 売買契約を締結する前に「住宅ローン特約(融資否決時の白紙解除)」を入れておくことが重要です。
■ 4. 本審査
- 事前審査を通過した後、正式にローンの本審査へ進みます。
- この際には「売買契約書」「登記簿謄本」「重要事項説明書」など、物件に関する資料も提出します。
■ 5. 融資承認 → 金銭消費貸借契約(ローン契約) → 決済・引渡し
- 審査に通れば、金消契約(借入契約)を交わし、物件の引き渡しと同時に融資実行されます。
■ 6.どんな人が借りられるのか(一般的な条件)
1.借入時20歳以上〜完済時80歳未満(多くは70歳未満)
2.年収400万円が一つの目安(銀行により異なる)
3.勤続年数:3年以上(1年でも借入可、転職したてでも条件付きで可)
4.信用情報:過去に延滞・債務整理(携帯電話、クレジットカードなど)があると難しい
不動産・保険の相談
- ◆不動産及び保険の相談
- (初回45分無料/2回目以降60分:4,950円)
不動産に関する暮らしと安心にお答えします
① 住宅ローンと家計管理
「ローンを組むと節約できる?」―賢い家計見直し術とは?
② 家賃保証制度の基礎知識
「連帯保証人なしでも借りられる時代へ」―保証会社の役割とは?
③ お子様のいないご夫婦の相続対策
「配偶者だけが相続するとは限らない!」―知っておきたい遺言と法定相続
④ 不動産購入時のプロのサポート
「不動産選びはプロと一緒に」―FP資格者が教える住まいとライフプラン
⑤ 建築・リフォームのご相談窓口
「住まいは買って終わりじゃない」―快適に暮らすための工事とメンテナンス
相続登記申請義務化
2024年4月1日から施行された「相続登記の申請義務化」について、ご説明します。
■相続登記の申請義務化とは?
これまで、不動産の相続が発生しても「相続登記(名義変更)」をしなくても罰則がなかったため、長年放置されるケースが多く問題となっていました。
そこで、2024年4月1日から、相続による不動産の登記(名義変更)が義務化され、一定期間内に申請しないと**過料(罰金)**が科されることになりました。
■何が義務化されたの?
不動産を相続した人(相続人)は、取得を知った日から原則3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
■いつから?
◆ 2024年(令和6年)4月1日 から適用されています。
■罰則は?
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■対象になる人は?
- 相続で土地や建物を取得した人(法定相続・遺言・遺産分割問わず)
- 複数の相続人がいる場合は、各相続人ごとに申請義務があります
■過去の相続にも適用されるの?
はい、過去の相続も対象になります。
たとえば、昔の相続で名義変更がされていなかった場合でも、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。
■簡略的な手続きもあります
登記申請が難しい方のために、簡易的な「相続人申告登記」制度もあります。
これは、「自分が相続人である」と法務局に申告するだけで、申請義務を果たしたことになります(ただし名義変更ではないので注意)。
■まとめ:
義務化開始日 2024年4月1日
申請期限 相続を知ってから3年以内
罰 則 10万円以下の過料
対 象 相続で不動産を取得した全ての人
対象範囲 施行前の相続にも適用あり
◆相続登記は、司法書士に依頼することが多く、手続きが煩雑な場合は、当社にご相談下さい
2025年リフォーム工事補助金申請について
リフォーム工事に関する補助金制度について、国や神奈川県、横浜市が提供する主な制度を以下にまとめました。詳細は各制度の公式サイトをご確認ください。
■ 国の主な補助金制度(2025年度)
1. 子育てグリーン住宅支援事業
- 対象工事:開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入
- 補助額:工事内容に応じて5万円~最大60万円/戸
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象。予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
- 備考:登録事業者が申請手続きを代行
2. 先進的窓リノベ2025事業
3. 給湯省エネ2025事業
- 対象工事:高効率給湯器の設置(エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームなど)
- 補助額:導入機器に応じて6万円~20万円
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象
- ■神奈川県の補助金制度
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金(令和7年度)
- 対象工事:既存住宅の窓、壁、天井、床の断熱改修
- 補助額:補助対象経費の1/3または20万円のいずれか低い額を上限
- 申請期間:令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで
- 備考:交付決定前に事業に着手した場合は補助金の交付対象外
■ 横浜市の補助金制度
1. 省エネ住宅住替え補助制度(リノベ型)
- 対象:窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅への住替え
- 補助額:基礎額70万円、市外からの転入で30万円加算、再エネ設備導入で50万円加算
- 2. 固定資産税・都市計画税の減額制度
- 対象工事:窓改修工事、床・天井・壁断熱工事、太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え・取付
- 減額内容:120㎡以下の場合、1/3減額(長期優良住宅の場合2/3減額)
■補助金制度の検索方法
地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度を検索できるサイトがあります。お住まいの市区町村の補助金制度を確認する際にご活用ください
- 住宅リフォーム支援制度検索サイト
リフォーム工事の補助金制度は多岐にわたり、条件や申請方法も異なります。詳細な情報や申請手続きについては、各制度の公式サイトやお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください
リースバック
「リースバック」は、自宅を売却して現金化し、そのまま賃貸として住み続ける仕組みです。老後資金や債務整理などの選択肢として注目されていますが、メリットもあればリスクもあります。
■ リースバックとは?
あなたが所有する家を不動産会社などに売却し、
その後「賃貸契約を結んで住み続ける」方式です
■リースバックのメリット(大丈夫な点)
① 現金化できる 不動産を売却して、老後資金・借金返済・事業資金などに充てられる
② 引越し不要 売却後も自宅に住み続けられるので、家族や生活への影響が少ない
③ 老後の資金計画に使いやすい 年金生活などで資金が心配な方にとって選択肢になりうる
④ 将来的に買い戻しも可能 条件を満たせば、自分の家を再び買い戻せる場合もある
(契約内容による)
⚠️ 注意点(気をつけるべき点)
① 売却価格が市場より安いことが多い 通常の売却より 2〜3割安くなるケースも
② 賃料が割高になる場合も 長く住み続けると、家賃負担が重くなることが
③ 住み続けられる保証はない 賃貸契約なので、更新されなければ 退去の可能性も
④ 買い戻し価格が高めに設定されがち 元の価格より高額になるケースもあるため要注意
■ リースバックは「大丈夫かどうか」の判断基準
✔ こんな人には向いている
- 老後の資金確保が急務
- 転居せずに生活を続けたい
- すでに子供に家を相続する予定がない
❌ 向いていないかもしれない人
- 売却益を最大化したい(普通に売った方が高く売れます)
- 家を最終的に残したい(賃貸では家が他人の所有物になる)
- 長期的に同じ家に絶対に住みたい
■ まとめ:リースバックは「手段のひとつ」
リースバックは「危険な制度」ではありませんが、目的と条件をしっかり整理してから選ぶべきサービスです。
不動産会社や金融機関によって条件は大きく異なるので、複数社から見積もり・比較するのがとても大事です!
必要であれば、「無料でリースバック診断してくれるサービス」や「信頼できる会社の見つけ方」などもご案内できますよ?
参考:国土交通省「住宅リースバックに関するガイドライン」
不動産無料相談所
神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています
■相模南支部 不動産無料相談所
- 開催日時:毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
- アクセス:小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
- 予約方法:完全予約制。電話、FAX、またはEメールで予約が必要です。
- 電話:042-743-3276
- FAX:042-749-1965
- Eメール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
- ■相模原市役所での不動産無料相談
相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。
中央区役所
- 開催日:第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:中央区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-769-8230
南区役所
- 開催日:第1月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:南区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-749-2171
緑区役所
- 開催日:第3月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:緑区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-775-1773
不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください
宅地建物取引業法第35条重要事項説明
宅地建物取引業法第35条および第35条の2の概要を説明します。
■宅地建物取引業法 第35条:重要事項の説明
目的:宅地や建物を売買・賃貸する契約の前に、買主や借主に対して「重要な事項」をきちんと説明する義務を定めています。
主なポイント:
- 宅地建物取引士が書面(重要事項説明書)を使って説明しなければならない。
- 主な説明事項には、以下のような内容が含まれます:
- 登記された権利関係(所有権・抵当権など)
- 法令による制限(都市計画法・建築基準法など)
- 私道の負担の有無
- 物件の概要(所在地、面積、構造など)
■宅地建物取引業法 第35条の2:環境確保に関する説明
目的:環境保全や住環境の安全に関する事項を取引前に明示する義務を追加しています。
主なポイント:
- 特定有害物質(土壌汚染、アスベストなど)の存在についての説明義務
- 周辺の生活環境(悪臭、騒音など)についての情報
- 自治体が定める条例などによる制限がある場合の説明
■補足
この2つの条文は、「取引の公正性」と「消費者の保護」を確保するために非常に重要な規定です。
特に第35条の説明は「重要事項説明」として、不動産業者の重要な義務とされています。
非公開会社再任登記と過料について
株式会社などの法人では、たとえ登記事項に変更がなくても、取締役などの任期が満了するたびに登記を行う必要があります。
特に、取締役の任期が10年(最長)とされている非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、実質的に「同じ内容でも10年ごとに再任登記が必要」となります
✅ 理由と根拠
- 会社法上、取締役や監査役などの役員の任期が満了すると、「退任」とみなされ、登記が必要です。
- たとえ再任(同じ人物が再度就任)であっても、任期の更新=新たな就任と扱われ、登記しなければなりません
- ■この登記を怠ると、前述のように過料(最大100万円)の対象となります
■対応例
- 任期満了 → 株主総会で再任決議 → 議事録作成 → 2週間以内に登記申請
建築計画概要書と記載事項証明書
■建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)
概要:
建築確認申請時に提出された建物の計画内容が記載された書類です。建築主事(または指定確認検査機関)が確認した計画内容が記載されています。
主な記載内容:
- 建物の所在地・用途・構造・規模(階数・延床面積など)
- 建築主や設計者の名前
- 建築確認番号、確認日
- 防火地域や用途地域などの法的制限情報
用途:
- 不動産購入時の物件調査
- リフォーム・建て替えの際の法的確認資料として利用
■記載事項証明書(きさいじこうしょうめいしょ)
正しい取得先:
➡ 市区町村の建築指導課など(※地域により名称は異なる場合あり)
概要:
建築基準法に基づき、確認済証や検査済証の内容などを証明する書類です。建築確認の記録に基づいて交付されます。
主な記載内容:
- 建築主・設計者・工事施工者
- 建物の構造・階数・延床面積
- 建築確認済証の番号・発行日
- 建築地の用途地域や制限
用途:
- 不動産売買や建築計画の説明資料
- 建て替え・リフォームの参考
- 建築物の法的情報確認に利用
■記載事項証明書が作られた理由
✅ 1. 法的効力を持つ「証明書」としての必要性
- 建築計画概要書は「単なる写し」や「参考情報」であり、法的な証明力は限定的です。
- 一方、「記載事項証明書」は行政が発行する正式な「証明書」として、法律・行政手続きで使えるように設計されています。
✅ 2. 不動産取引や金融機関とのやり取りでの利用
- 売買契約やローン申請など、正式な証明書が求められる場面では、建築計画概要書では不十分です。
- そのため、建築確認の事実を公的に「証明」する書類として、記載事項証明書が必要になります。
✅ 3. トラブル防止の観点
- 建物の構造や面積、確認番号などを公的に証明することで、不動産取引におけるトラブル(虚偽申告・誤解)を防ぐことができます。
■ 結論:目的に応じた「使い分け」が大切
建築計画概要書 情報確認・参考資料として活用 △ 参考レベル
記載事項証明書 行政・金融手続きでの正式書類提 ◎ 公式証明書
遺産分割協議書
「遺産分割協議書」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように相続するかを相続人全員で話し合い、書面にまとめたものです。
■主なポイント
- 法的効力
遺産分割協議書は、相続登記や預金払い戻しなど、法的な手続きをする際に必要になります。 - 記載内容
- 被相続人の情報(氏名・死亡日)
- 相続人全員の氏名と住所
- 分割内容(どの財産を誰が相続するか)
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付
- 注意点
- 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると無効)
- 財産内容が不明確だと後にトラブルになることも