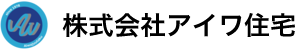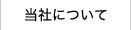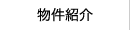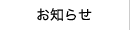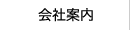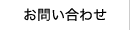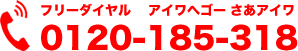建蔽率容積率
建ぺい率(けんぺいりつ)と容積率(ようせきりつ)は、土地にどれだけ建物を建てられるかを定める重要な指標で、都市計画法および建築基準法によって規定されています
■ 建ぺい率(けんぺいりつ)
■ 定義
「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のこと
■ 計算式
建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50%
■容積率(ようせきりつ)
■定義
「敷地面積に対する延べ床面積(各階の合計床面積)の割合」のこと。
■ 計算式
容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、延べ床面積が150㎡なら、容積率は150%
■ 規制内容は用途地域ごとに異なる
第一種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100%または200%
商業地域 建ぺい率80% 容積率400%または500%
工業地域 建ぺい率60% 容積率200%または300%
※角地や防火地域の条件によって緩和される場合あり。
■土地を買う前、家を建てる前には、必ず都市計画図や役所の確認が必要です。
道路幅員による容積率制限とは
1. 道路幅員による容積率制限とは
建築基準法第52条第2項では、敷地が接している道路の幅が狭いと、建物の容積率(延べ床面積の制限)が自動的に下がるというルールがあります。
これは、日照・採光・通風などを確保するためです。
2. 基本ルール
容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、道路幅員による制限値の小さい方が適用されます。
道路幅員による制限値は、以下の式で計算します。
容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数容積率の限度 = 道路幅員(m) × 制限倍数容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数
この制限倍数は、用途地域によって異なります。
3. 制限倍数
- 住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)
→ 倍数は 4/10(=0.4)、つまり「道路幅員 × 0.4 × 100」でパーセント化
例:道路幅6mなら 6 × 0.4 × 100 = 240% - その他の用途地域(近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用)
→ 倍数は 6/10(=0.6)
例:道路幅6mなら 6 × 0.6 × 100 = 360%
4. 適用例
- 用途地域:第一種住居地域(倍数0.4)
- 指定容積率:300%
- 道路幅員:5m
計算:5 × 0.4 × 100 = 200%
→ この場合、300%ではなく**200%**が容積率の上限となります。
5. 注意点
- 接道している道路が複数ある場合は、幅員が最も広い道路側で計算します。
- 前面道路が4m未満の場合は、セットバック後の幅員で計算します。
- 指定容積率が道路幅員制限より低ければ、道路幅員制限は関係ありません。
斜線制限とは
1. 斜線制限とは
建物の高さを、一定の角度で制限する規定です。
周囲の日照・採光・通風を確保するために、建築基準法で定められています。
大きく分けて 3種類 あります。
2. 種類と内容
(1) 道路斜線制限
- すべての用途地域に適用
- 建物は、前面道路の反対側境界線から一定の角度で引かれた斜線内に収まる必要があります
- 基本は、道路中心線から1.25倍の高さまで(用途地域で係数や緩和あり)
- 例:幅員8mの道路 → 高さ制限は概ね10m(8m ÷ 2 × 1.25)
(2) 隣地斜線制限
- 住居系用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用など)に適用
- 隣地境界線から一定の角度で制限
- 開始高さは、第一種低層住居専用地域なら5m、中高層住居専用地域なら10mが一般的(自治体により異なる)
(3) 北側斜線制限
- 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用
- 北側隣地の日照確保のため、北側境界線から一定の角度で制限
- 開始高さは5mまたは10m、角度は1.25倍または1.5倍など自治体で設定
3. 緩和や例外
- 防火地域・準防火地域で耐火建築物にする場合は緩和あり
- 角地や道路幅員が広い場合、制限が緩やかになることがある
- 地区計画や高度地区の指定がある場合は、その規定が優先
4. 実務上のポイント
- 建築設計時は、建物の断面図に斜線を描いて確認するのが基本
- 道路・隣地・北側の制限が同時にかかることもあるため、組み合わせの検討が重要
地区計画
■地区計画とは?
- ●住民によるまちづくりルールの提案をもとに、市が都市計画として決定する制度です。
- ●建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面位置や建物高さなどの制限が条例で定められます。
- ●区域内で建築・工作物の着手前には、30日前までに市へ届出が必要です。
■地区計画の主な規制例
- ●御園二丁目地区
低層住宅主体の居住地域を対象とした地区計画です。
- 敷地面積の最低限度:90㎡
- 壁面の後退:境界線から0.5m以上
- 建築物の最高高さ:A地区10m以下/B地区12m以下
- 色彩についても景観配慮の指針があります。
- ●橋本駅南口地区
再開発区域として、商業・業務と住宅の高度利用を目指し、歩道状空地の整備や用途用途・意匠の制限があります。 - ●相模台通り地区
座間市と相模原市の境界近くにあり、商業集積の形成を目的とした規制を定めています。
※相模原市は、東林間駅前地区、田名塩田原地区、緑が丘地区、橋本駅南口地区、大野台3丁目地区、 橋本6丁目地区、相模台通り地区、古淵駅周辺地区、原当麻駅東口地区、南台4丁目地区、しおだ地区、リバティ大通り地区、氷川通り地区、橋本都市拠点地区、田名久所地区、 橋本3丁目地区、桜台地区などがあります。
民法と借地借家法の退去通知
民法第617条(令和2年改正後の条文)
この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。
特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。
■第617条(賃貸借の解約申入れ)
第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる。
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、
- 建物の賃貸借では3か月
- 土地の賃貸借では1年
を経過することによって、契約は終了する。
■要点まとめ
①期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)
②当事者はいつでも通知できる
③建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後
④この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます
▲借地借家法との関係
①借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません。
- ②正当事由が必要
- ③通知は原則6か月前
- ④借主の保護が優先される
■「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です
重要土地等調査法
■相模原市における「重要土地等調査法」の指定状況
相模原市については、重要土地等調査法(令和3年法律第84号)に基づき、以下のように指定が行われています。
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)」
■安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地利用の防止
- 注視区域の対象地
- 神奈川県相模原市には、防衛関係施設である陸上装備研究所および相模総合補給廠が存在し、その周囲おおむね1,000m以内が「注視区域」として指定されています。
- この注視区域は町田市の一部地域とともに対象となっており、相模原市内の該当するエリアも含まれます。
- 特別注視区域の指定状況
- 相模原市では、座間市に位置するキャンプ座間(座間駐屯地)周辺が主として「特別注視区域」に該当します。
■注意点・補足
- 「注視区域」は届出義務は課されませんが、国による土地・建物の利用状況調査が行われる可能性があります。
- 「特別注視区域」の場合、200㎡以上の土地売買等には国への届出義務があります。
- 指定状況は今後の法令改正や区域の追加により変動する可能性がありますので、正確には内閣府や自治体(神奈川県・相模原市)の公式発表資料をご確認ください。
■今後の確認方法
- 相模原市公式サイトの基地対策課や内閣府の重要土地調査法に関する専用ページで告示の内容や図面を確認できます。
- 特定の町丁目や土地について指定対象かを調べたい場合は、内閣府コールセンター(0570‑001‑125/平日 9:30〜17:30)へお問い合わせされることをおすすめします。
65歳以上の介護をしている方へ
■介護をしている65歳以上の方へ ~介護認定とケア施設の利用について~
介護をされている方の中には、ご自身が心身ともに疲れを感じている方もいらっしゃると思います。そんな方には、介護認定の申請やケア施設への通所をおすすめします。
なぜ介護認定の申請がおすすめなのか
介護を続けていると、知らず知らずのうちに疲れがたまり、身体の動きが鈍くなったり、うっかりミスが増えたりすることがあります。そのような状態が続くと、
要支援1などの認定を受けられる可能性があります。
介護認定を受けることで、心身のリフレッシュが可能になり、自分自身を大切にする時間が確保できます
■申請に必要なもの
介護認定の申請には、医師の診断書が必要です。まずはかかりつけの医師に相談してみましょう
■要支援1の認定を受けた場合
- ケア施設に通所できるようになります。
- 利用料の自己負担は1割~3割(保険適用)です。
- 月に1度、半日だけなど、ご自身の体調にあわせてスケジュールを組むことができます。
- 軽い運動やレクリエーション、相談などを通して、心身のケアが受けられます。
ケアマネジャーや施設のスタッフと相談しながら、無理のない範囲で安心して利用できます
■介護認定を申請できる人
- 65歳以上(第1号被保険者):日常生活で支援や介護が必要な方
- 40~64歳(第2号被保険者):加齢に伴う特定疾病により介護が必要になった方
■申請方法
申請は、以下の方法で行えます:
- 本人またはご家族
- 地域包括支援センター(高齢者支援センター)
- ケアマネジャー
- 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に代行してもらうことも可能です。
ご自身の健康と生活の質を守るためにも、早めの申請を検討されることをおすすめします。何か不安なことがあれば、お近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談ください
配偶者居住権
「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について、ご説明します。
■配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなるまで、または一定期間、無償でその住まいに住み続けられる権利です。
これは、2020年(令和2年)4月1日に施行された新しい制度で、高齢の配偶者の住まいを守るために導入されました。
■なぜ必要になったの?
これまでの制度では、住んでいた家も相続財産の一部として分割対象になるため、配偶者が「家を失う」リスクがありました。
特に、子どもとの遺産分割協議で不利な立場になることも…。
■そこで「配偶者の住む権利」を独立して保護するために、この制度が導入されました。
■どんな権利なの?
居住権の性質 所有権と別に設定される「使用権」
無償で住める 家賃などは不要
第三者に売却不可 譲渡・売却できない(保護目的の為)
法的保護あり 登記すれば第三者に対抗可能
■取得の方法は?
配偶者居住権は、以下のどちらかで取得できます。
- 遺産分割協議で定める
- 遺言で指定されている場合
■いずれの場合も、法務局で登記することで権利が保護されます。
■例で説明(簡単なケース)
夫が亡くなり、妻と子が相続人。
夫婦が住んでいた家の評価額は3,000万円。
【従来の方法】
妻が家を相続するなら、3,000万円分の他の財産が相続できなくなる(バランスが取りにくい)
【配偶者居住権を使った場合】
- 妻が「住む権利(配偶者居住権)」を取得 → 評価額はたとえば1,200万円
- 残りの1,800万円分の家の所有権は子どもに → 財産の分け方が柔軟になる
■メリット・デメリット
メリット
高齢の配偶者の住まいを確保できる
財産の分け方が柔軟になる
デメリット
不動産の評価や分割が複雑になる
家を売って現金化しにくくなる
■まとめ
- 2020年に施行された新しい制度
- 配偶者の「住まいを守る権利」として注目
- 相続人間のトラブル防止にも有効
- 遺言や遺産分割協議での事前の合意がポイント
私道使用承諾書
「私道掘削制限の緩和」とは、私道の下にライフライン(上下水道・ガス・電気など)を通すための工事を、一定の条件下で許可・緩和する措置のことです。
本来、私道は「私人の所有地」なので、勝手に掘削(=地面を掘ること)することはできません。
■ 私道掘削とは?
私道(私有地)に配管などを埋設したり、交換・修理するために地面を掘る行為のことです。
▲通常の私道掘削の制限
▲所有者の承諾が必要
掘削するには私道の所有者全員の書面による同意(私道承諾書)が原則必要
▲同意が得られないと工事できない
一人でも拒否する人がいれば、ライフラインの整備ができず、建築や居住に大きな支障が。
■掘削制限の緩和措置とは?
所有者の同意が得られない場合でも、公共の福祉やライフライン確保のために、一定条件で掘削を認める制度があります。
代表的な制度・方針
▲自治体による行政指導
「どうしても必要な工事」であると判断された場合、自治体が調整・指導を行うことがあります
▲都道府県・市区町村の条例・ガイドライン
一部自治体では、特定の要件を満たす場合に、私道掘削を認める規定を設けています
▲公共性の高い工事の場合
上下水道など、公益性の高いインフラ整備は、特例的に掘削が許可される場合があります
■ 緩和が認められるケースの一例
- 周辺の住民が最低限の生活インフラを必要としている
- 私道の使用が「不可避」で、他に代替手段がない
- 掘削部分の復旧が保証されている
- 掘削工事による私道の機能低下がないことが確認されている
■ 手続きの流れ(一般例)
- 掘削の目的・範囲を明示した計画書を作成
- 私道所有者への同意取得(できる範囲で)
- 自治体(市区町村)の道路管理課や建築指導課に相談
- 必要に応じて「特例承認」または「公共工事としての執行申請」へ進む
■ 注意点
- 緩和はあくまで例外措置で、自治体の判断に強く依存します。
- 私道の所有者が反対している場合は、裁判や調停に発展する可能性も。
- 掘削後の原状回復(舗装など)や近隣対応も大切です。
■ まとめ
「私道掘削制限の緩和」は、公私のバランスをとりながら、地域生活のインフラ整備を現実的に進めるための手段です。ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、事前に自治体への相談・調整が不可欠です。
必要であればあなたの自治体におけるガイドラインを調べたり、相談窓口をご案内することもできます。
参考資料:
- 東京都都市整備局 私道掘削に関する対応
- 各市区町村「私道掘削ガイドライン」等
相続で空家をお持ちの方へ
【相続で空き家をお持ちの方へ】
相続後、使われずに放置されている空き家でお困りではありませんか?
■固定資産税の負担が重い
■売却や活用方法がわからない
■ご近所への迷惑が気になる
■解体すべきか悩んでいる
相続によって発生した空き家は放置していると、資産価値の低下や近隣トラブルにつながる恐れもあります。
早めのご相談で、最適な活用・管理・売却の道が開けます。
私たちは、空き家問題に精通した専門家として、相談を受け付けております。
法律・税金・不動産の観点から、あなたの状況に合わせたご提案をいたします